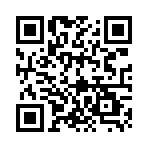2007年01月20日
QED ハンドル長の問題
(タイトル元ネタ:「QED ベイカー街の問題」/高田崇史著/QEDシリーズ第3作 超オススメ!!)
う~ん、前回の記事は、いまいち説明不足・・・だったのかどうかよくわかりませんが、もう少し説明を追加してみることにします。
なにせ考えれば考えるほど、ハンドル1巻きあたりの巻き取り量というのは、
としかいえない気がしてきたものですから。
まずこういったことを考えるときには基準を決めなければなりません。
リールは巻き取るのが仕事です。
そしてその中で注目すべき点としては、巻き取り速度でしょう。
エリアフィッシングでは特に、一定速度のリトリーブやデッドスローリトリーブが重要などと、とかく速度の話がよく出てきますしね。
で、巻き取ると言う行動は何かと言うと、考えるまでもなく、ハンドルを回す行為に他なりません。
さて、一定速度のリトリーブをするには、ハンドルをどう回せばよいでしょうか?
ここで深く考えてもらっても困るのですが、普通に考えれば、一定速度でハンドルを回せばいいわけです。
さて問題です。
リールのカタログに、巻き取り速度について書かれているでしょうか?
まったく書かれていませんね~。
まあいったんそれは置いておいて・・・
速度の計算式は、さすがに中学校レベル(小学校かも?)の数学で出てきますよね。
距離÷時間です。
さてハンドルを回す速度について考えると、1秒間に1回転させるとして、45mmのハンドルではどうなるでしょうか。
ハンドルの移動距離を考えると半径45mmの円を考えれば良いわけで、
ですよね。つまり
となるわけです。
そのときに巻き上げられる巻取り量を1秒で割ったものが、巻き取り速度になるわけですね。
ということで、ステラ1000Sと1000PGSDHを考えてみると
1000S = 90πmm/秒 : 61cm/秒
1000PGSDH = 76πmm/秒 : 52cm/秒
ここでひとついえるのが、1秒間にハンドル1回転させる場合、ハンドル長が長いほうがハンドルを回す速度が速いんですね。
当たり前のことですが。
そしてあらためて二つを比較するときに、もし同じハンドル速度で巻いた場合はどうなるの?
という疑問がわいてくるはずです。
つまり1000PGSDHを90πmm/秒の速度でハンドルを巻くとどうなるか?
両辺に同じ数字を掛けても比率の式は成り立つので、90/76を両辺に掛けると
と言う結果になります。
つまりステラ1000Sを1秒間に1回転させたときのハンドルを回す速度で、1000PGSDHのハンドルを回すと、1000Sの巻き取り速度よりも0.58cm/秒ほど速い速度で巻き取られると言うことになるわけです。
パワーギアでデットスローリトリーブを実現するといいながらも、実際のところは、1000Sのほうが巻き取り速度が遅いという、見事な間違いをカタログで展開してくれているわけなんですね・・・
結構ショック受けません?
今回は順を追って書いたし、具体的にステラ1000Sと1000PGSDHを比較してみたのでわかりやすかったと思うのですが、どうでしょうかね。
でも、忘れちゃならないのがハンドル自身の重さにかかる重力の影響や位置エネルギーの影響があるので、ハンドル長を変えてPGやHGと同じスペックにしたとしても、実際のところはまったく同じと言うわけにはなりませんし、ハンドル長を変えることによる巻きにくさの影響も見落とせませんので、実はやはりこういったPGやHGの存在意義はあるわけです。
例えば、ハンドル長を短くして手首の回転だけで簡単に、でも同じ巻き取り速度でリトリーブができるようにしたいと考えたときに、そのままハンドル長を短くすると事実上のハイギア化がされて巻き取り速度が上がってしまうわけですが、PGのリールがあれば、それにハンドル長の短いものを取り付けることで、目的が実現できてしまうわけですね。
そういった意味も含めて、リールのカタログ上でハンドル1巻きあたりの巻き取り量だけをリールのする仕事のスペックとして記載していること自体、まったく意味をなしていないと気がついたわけです。
デジカメの話をしましょう。
デジカメを買うときに、いろいろとスペックを比較すると思いますが、大体レンズの画角(焦点距離)をみますよね。
画角って、あの35mm~105mm光学3倍ズームとかって書いてある部分ですよ。
さて、もしデジカメを持っていたら、レンズのところを見てみましょう。
そんな大きな数字は書いていないことに気がつくでしょう。
あのデジカメの表記は、35mmフィルム換算で書いてあるんですよ
ちゃんとカタログに記載されていると思いますが、みんな深く考えずに、普通に撮っているカメラのレンズとしてはこういう性能なんだろうと思っているでしょう。
そういった普通に使っているカメラという基準に対して、こういった性能であると認識した上で、購入しているんですね。
じゃあ、リールにはそういった基準がないの?
・・・私の見た限りじゃなさそうですね~。(一般に認知されているというレベルでは)
もし、デジカメを買おうとしたときに、レンズの性能だけが記載されていたら・・・
つまり35mmフィルム換算の数値抜きにして、例えば4.6mm~33mmの画角ですと書いてあったら・・・
他に見た目はまったく同じような印象を受けるのに、5.8mm~17.4mmと書いてあるカメラがあったら・・・
普通の人がきちんと判断して買えますか?
ちなみに、この数字は某社のデジカメの実際の数字で、35mmフィルム換算にすると、最初のものは28mm~200mmで、後のものは28mm~85mmとなり、ようやく比較できる状態になるわけです。
つまり、この4.6mm~33mmといったそもそものレンズの性能にあたる部分が、リールで言えばハンドル1回転あたりの巻き取り量にあたると考えたらわかりやすくなるんですね。
(正確にはギア比の部分だけですが、まあわかりやすくする意味で)
つまり、このデジカメの例でわかるように、リールのカタログって、デジカメで言えば比較のしようがないレンズ自体の性能のみのスペック表示をされた状態で、しかも何らかの基準に自分で計算しなおそうにもその材料すら与えてくれないような
って状態で書かれていたんですね。
いままでそれをなんだかわかったような気がして買っていた自分がちょっと悲しい・・・
ということであえて基準を設けて比較していかなければならないわけで、前回から時々使っている表現、ハンドル長45mm換算というのは、デジカメで言うと35mmフィルム換算と同じ意味合いだったんですよ。
つまりハンドル長も含めた計算をしないと、リールの本来のスペックはわからないということです。
換算する基準をどうするかは難しいですが、きちんと対応してほしいものですね。
これが最初に書いた、性能表示として不適格ということの理由です。
以上QED(証明終わり!?)
なお、別にメーカーに対して文句を言っているとか、リールに対して文句があるとかではなく、リールの性能を考える際に、参考にしてみてね、と言う程度の話を重そうに書いてみただけですので、あまり深く考えすぎないでくださいね~。
でも、性能表示にハンドル長は追加して欲しいですけどね~。
う~ん、前回の記事は、いまいち説明不足・・・だったのかどうかよくわかりませんが、もう少し説明を追加してみることにします。
なにせ考えれば考えるほど、ハンドル1巻きあたりの巻き取り量というのは、
性能表示として不適格
としかいえない気がしてきたものですから。
まずこういったことを考えるときには基準を決めなければなりません。
リールは巻き取るのが仕事です。
そしてその中で注目すべき点としては、巻き取り速度でしょう。
エリアフィッシングでは特に、一定速度のリトリーブやデッドスローリトリーブが重要などと、とかく速度の話がよく出てきますしね。
で、巻き取ると言う行動は何かと言うと、考えるまでもなく、ハンドルを回す行為に他なりません。
さて、一定速度のリトリーブをするには、ハンドルをどう回せばよいでしょうか?
ここで深く考えてもらっても困るのですが、普通に考えれば、一定速度でハンドルを回せばいいわけです。
さて問題です。
リールのカタログに、巻き取り速度について書かれているでしょうか?
まったく書かれていませんね~。
まあいったんそれは置いておいて・・・
速度の計算式は、さすがに中学校レベル(小学校かも?)の数学で出てきますよね。
距離÷時間です。
さてハンドルを回す速度について考えると、1秒間に1回転させるとして、45mmのハンドルではどうなるでしょうか。
ハンドルの移動距離を考えると半径45mmの円を考えれば良いわけで、
2×円周率(π:パイ)×半径
ですよね。つまり
90πmm
となるわけです。
そのときに巻き上げられる巻取り量を1秒で割ったものが、巻き取り速度になるわけですね。
ということで、ステラ1000Sと1000PGSDHを考えてみると
1000S = 90πmm/秒 : 61cm/秒
1000PGSDH = 76πmm/秒 : 52cm/秒
ここでひとついえるのが、1秒間にハンドル1回転させる場合、ハンドル長が長いほうがハンドルを回す速度が速いんですね。
当たり前のことですが。
そしてあらためて二つを比較するときに、もし同じハンドル速度で巻いた場合はどうなるの?
という疑問がわいてくるはずです。
つまり1000PGSDHを90πmm/秒の速度でハンドルを巻くとどうなるか?
90/76 × 76πmm/秒 : 90/76 × 52cm/秒
両辺に同じ数字を掛けても比率の式は成り立つので、90/76を両辺に掛けると
90πmm/秒 : 61.58cm/秒
と言う結果になります。
つまりステラ1000Sを1秒間に1回転させたときのハンドルを回す速度で、1000PGSDHのハンドルを回すと、1000Sの巻き取り速度よりも0.58cm/秒ほど速い速度で巻き取られると言うことになるわけです。
パワーギアでデットスローリトリーブを実現するといいながらも、実際のところは、1000Sのほうが巻き取り速度が遅いという、見事な間違いをカタログで展開してくれているわけなんですね・・・

結構ショック受けません?
今回は順を追って書いたし、具体的にステラ1000Sと1000PGSDHを比較してみたのでわかりやすかったと思うのですが、どうでしょうかね。
でも、忘れちゃならないのがハンドル自身の重さにかかる重力の影響や位置エネルギーの影響があるので、ハンドル長を変えてPGやHGと同じスペックにしたとしても、実際のところはまったく同じと言うわけにはなりませんし、ハンドル長を変えることによる巻きにくさの影響も見落とせませんので、実はやはりこういったPGやHGの存在意義はあるわけです。
例えば、ハンドル長を短くして手首の回転だけで簡単に、でも同じ巻き取り速度でリトリーブができるようにしたいと考えたときに、そのままハンドル長を短くすると事実上のハイギア化がされて巻き取り速度が上がってしまうわけですが、PGのリールがあれば、それにハンドル長の短いものを取り付けることで、目的が実現できてしまうわけですね。
そういった意味も含めて、リールのカタログ上でハンドル1巻きあたりの巻き取り量だけをリールのする仕事のスペックとして記載していること自体、まったく意味をなしていないと気がついたわけです。
デジカメの話をしましょう。
デジカメを買うときに、いろいろとスペックを比較すると思いますが、大体レンズの画角(焦点距離)をみますよね。
画角って、あの35mm~105mm光学3倍ズームとかって書いてある部分ですよ。
さて、もしデジカメを持っていたら、レンズのところを見てみましょう。
そんな大きな数字は書いていないことに気がつくでしょう。
あのデジカメの表記は、35mmフィルム換算で書いてあるんですよ
ちゃんとカタログに記載されていると思いますが、みんな深く考えずに、普通に撮っているカメラのレンズとしてはこういう性能なんだろうと思っているでしょう。
そういった普通に使っているカメラという基準に対して、こういった性能であると認識した上で、購入しているんですね。
じゃあ、リールにはそういった基準がないの?
・・・私の見た限りじゃなさそうですね~。(一般に認知されているというレベルでは)
もし、デジカメを買おうとしたときに、レンズの性能だけが記載されていたら・・・
つまり35mmフィルム換算の数値抜きにして、例えば4.6mm~33mmの画角ですと書いてあったら・・・
他に見た目はまったく同じような印象を受けるのに、5.8mm~17.4mmと書いてあるカメラがあったら・・・
普通の人がきちんと判断して買えますか?
ちなみに、この数字は某社のデジカメの実際の数字で、35mmフィルム換算にすると、最初のものは28mm~200mmで、後のものは28mm~85mmとなり、ようやく比較できる状態になるわけです。
つまり、この4.6mm~33mmといったそもそものレンズの性能にあたる部分が、リールで言えばハンドル1回転あたりの巻き取り量にあたると考えたらわかりやすくなるんですね。
(正確にはギア比の部分だけですが、まあわかりやすくする意味で)
つまり、このデジカメの例でわかるように、リールのカタログって、デジカメで言えば比較のしようがないレンズ自体の性能のみのスペック表示をされた状態で、しかも何らかの基準に自分で計算しなおそうにもその材料すら与えてくれないような
何をどう判断して考えればいいんだってばさ!!
って状態で書かれていたんですね。
いままでそれをなんだかわかったような気がして買っていた自分がちょっと悲しい・・・
ということであえて基準を設けて比較していかなければならないわけで、前回から時々使っている表現、ハンドル長45mm換算というのは、デジカメで言うと35mmフィルム換算と同じ意味合いだったんですよ。
つまりハンドル長も含めた計算をしないと、リールの本来のスペックはわからないということです。
換算する基準をどうするかは難しいですが、きちんと対応してほしいものですね。
これが最初に書いた、性能表示として不適格ということの理由です。
以上QED(証明終わり!?)
なお、別にメーカーに対して文句を言っているとか、リールに対して文句があるとかではなく、リールの性能を考える際に、参考にしてみてね、と言う程度の話を重そうに書いてみただけですので、あまり深く考えすぎないでくださいね~。
でも、性能表示にハンドル長は追加して欲しいですけどね~。
2006年07月06日
スプーンにかけろ!?(1)
タイトルは、まああまり気にしないで^^;
とりあえず、自分のスプーン釣りについて、いろいろと書いてみようかなと思って、こんな企画(?)をはじめてみました。
まあ、初心者に毛が生えた程度の自分のレベルでこんなことを書くのもおこがましいとも思いつつ、まあ、こんなことでも書いてないと、ネタもないもので^^;
てことで、記念すべき第1回は・・・
皆さんもきっと、スプーンでいろいろと誘いをやっているかと思いますが、人それぞれに工夫があるかと思います。
一応自分でも工夫らしきものをして誘いをかけているのでその紹介をしてみましょう。
でも、誘いをかける前に必要なことといえばやはり・・・
等速リトリーブ
ですね。
これができなきゃ、誘いもへったくれもないし。
私は、エリアフィッシング(ルアーフィッシング)をはじめてから、およそ3ヶ月は、誘いもなにもなく、ひたすらこの等速リトリーブの練習に明け暮れていました。
とにかくラインであたりを取るとか、サイトフィッシングとかそういったものは、ほとんどそっちのけで、リールのハンドルを見ながらリトリーブしたり、また、時々は目をつぶってちゃんと集中して巻けているかとか、水面に視線を移しても、ちゃんと巻けているかとか、とにかく意識して徹底的に等速で巻ける練習をしていました。
この練習の最中でも、手元にくるあたりはちゃんと合わせて魚もゲットできますし、この当時から、等速リトリーブができるようになってくるほど、バイト率も上がってきているような感じで、やはりこの基本は大事だなと、今でも思っています。
これができるようになって、次はサイトやらラインであたりを取れるようにして、最後にスプーンにアクションをつけるという順で、自分の釣りを発展させてきました。
そうですね~、ラインであたりが取れるようになったあたりから、エリアフィッシングのDVDとかを見始めて、NeiちゃんのスプーンスタイルのDVDや雑誌から、まずは基本のアクションと、そしてその応用の自分なりのアクションに発展させてきて、今の自分なりのアクションが生まれてきたかなと。
ちなみに、自分独自(かどうかは知りませんが、とりあえず自分で思いついたもの)のアクションの名前については、結構適当につけています。
ネーミングセンスがないのは、まあご愛嬌で^^;
ということで、今自分が主に使っている、スプーンのアクションをご紹介です。
カット:
これは、雑誌にもNeiちゃんのスプーンスタイルのDVDにも載っていましたが、単純に竿先を軽く上に跳ね上げるアクションですね。
一瞬ルアーが今までリトリーブしていた泳層のやや上に跳ね上がり、その後またもとの泳層へ戻るようなアクションらしいです。
なんというか、実に手っ取り早いアクションですね。
でも本当にこれを有効に使うためには、とにかく等速リトリーブが出来ていないと、まったく役に立たないかと思われます。
ちなみに、空あわせもこのアクションに分類されるかな!?(笑)
空あわせ後にも、よくバイトありますしね^^
ここからが、一応自分なりの応用編で、もしかしたら自分の知らないところで既出なのかもしれませんが、一応自分で考えたアクションです。
ダウンカット(仮):
カットが上に跳ね上げる動作に対して、下に向かってカットしています。
アクション的にはトゥイッチングに近いような、でもそれよりもぜんぜん軽い操作で行っています。
本当に竿先を、ピッと弾くような感じで。
ルアーの動きとしては、おそらく一瞬だけダッシュしてその後に一瞬だけ停止するような動作になっているかと思います。
おそらく下にカットする分、ルアーの浮き上がりは抑えられているはず。
カットと適宜組み合わせて使っています。
ホイップ(仮):
これは、ダウンカットを小さくやっているうちに生まれたアクションですね。
表層から中層でも上のほうで使っています。
どういうアクションかというと、竿先を細かく上下にカットするのですが、その際に竿先から水面まで延びているラインをムチのように上下に震わすような感じでアクションをつけています。
ラインで水面を軽くたたくようなイメージでしょうか。
ちょっと表現が難しいなぁ。
ルアーに対して直接アクションをかけるイメージではなく、ラインを動かすような軽いタッチで行います。
一応サイトで動きを確認すると、通常のスプーンのアクションに加えて、頭の部分が軽く上下しているようなアクションに見えました。
まあまだ研究中のアクションなので、どこまで有効で、本当にそんなアクションをし続けているのか、といった部分は未知数です。
スラッキング(仮):
これがまた偶然から生まれたもので、これについては自分の中ではかなり有効なアクションとして使っています。
やり方はいたって簡単で、普通にリトリーブしながらラインスラックを作るだけです。
要はリトリーブしつつ、時々竿先を水面まで落として、再び持ち上げるだけですね。
(ほんとうにラインスラックを作るだけ)
コツとしては、あまりすばやくやらないで、よっこいしょ、ってなくらいに落ち着いてやることでしょうか。
ルアーにかかるアクションとしてはおそらく、
一瞬停止>軽くダッシュ>一瞬停止>再度軽くダッシュ>通常速度
というような動きになっているかと思われます。
カットのようにバランスを崩すようなすばやい動きではないです。
大体このアクションで魚がバイトしてくるタイミングは、一番最後の通常のリトリーブ速度に戻る寸前あたりになります。
時々、最初の軽くダッシュ(竿先を水面につけようと落としている最中)でバイトがありますが、圧倒的に最後のラインスラックの完成したとき、つまり通常のリトリーブ位置に竿のポジションが戻った瞬間にバイトがあります。
ここまで読めば、どういった偶然で生まれたかは容易に予想できるかと思いますが、ラインであたりを取る際に、ラインスラックがあるとラインが見やすいというのはよくあることで、そのときも最初からラインスラックを作ってリトリーブしていました。
すると、途中でラインが見難くなってきたので、ラインスラックを作ろうと再度水面まで竿先を落として、持ち上げたその瞬間にバイトがあり、そのままゲットできました。
まあこれだけですと偶然だろうということで終わるのですが、このときはまったくこういったアクションについては無関心なときだったので、何も考えずにキャストを繰り返し、何も考えずにラインスラックを作り直し、その作り直し終わった瞬間にまたばかすかとバイトがあり、まさに爆釣状態に入ったため、後日あらためてそのときの状況を思い出してみると、偶然とは思えないほどの同じタイミングでのバイトということにようやく気がつきました。
その後も、慎重に他のエリアでもこのアクションを試してみたのですが、釣果のばらつきはあるものの、バイトがあるタイミングはほぼ同じで、これはもしかしてなかなか有効なアクションなのではないかと、とりあえず自分のメインのアクションとして使おうかなと思ったわけです。
どっちかというと、若干活性があるほうが、このアクションは有効っぽいかなと感じていますが、そこまではよくわかっていません。
はてさて一応自分が使っているスプーンのアクションを紹介してみましたが、こういったアクションでかかるかどうかは、そのときのお魚さんの気分によるので、アクションによる誘いが効かないときは、ぜんぜん効かないということはよくあるかと思います。
私は、そのときはあっさりとクランクに移行しちゃっています(笑)
えぇ、やっぱり楽しく簡単?に釣れればそれにこしたことはないですからね
てことで、素人に毛が生えた程度の考察でしたが、笑い飛ばしながらも参考にしてみてはいかが?
とりあえず、自分のスプーン釣りについて、いろいろと書いてみようかなと思って、こんな企画(?)をはじめてみました。
まあ、初心者に毛が生えた程度の自分のレベルでこんなことを書くのもおこがましいとも思いつつ、まあ、こんなことでも書いてないと、ネタもないもので^^;
てことで、記念すべき第1回は・・・
スプーンで誘え!!

皆さんもきっと、スプーンでいろいろと誘いをやっているかと思いますが、人それぞれに工夫があるかと思います。
一応自分でも工夫らしきものをして誘いをかけているのでその紹介をしてみましょう。
でも、誘いをかける前に必要なことといえばやはり・・・
等速リトリーブ
ですね。
これができなきゃ、誘いもへったくれもないし。
私は、エリアフィッシング(ルアーフィッシング)をはじめてから、およそ3ヶ月は、誘いもなにもなく、ひたすらこの等速リトリーブの練習に明け暮れていました。
とにかくラインであたりを取るとか、サイトフィッシングとかそういったものは、ほとんどそっちのけで、リールのハンドルを見ながらリトリーブしたり、また、時々は目をつぶってちゃんと集中して巻けているかとか、水面に視線を移しても、ちゃんと巻けているかとか、とにかく意識して徹底的に等速で巻ける練習をしていました。
この練習の最中でも、手元にくるあたりはちゃんと合わせて魚もゲットできますし、この当時から、等速リトリーブができるようになってくるほど、バイト率も上がってきているような感じで、やはりこの基本は大事だなと、今でも思っています。
これができるようになって、次はサイトやらラインであたりを取れるようにして、最後にスプーンにアクションをつけるという順で、自分の釣りを発展させてきました。
そうですね~、ラインであたりが取れるようになったあたりから、エリアフィッシングのDVDとかを見始めて、NeiちゃんのスプーンスタイルのDVDや雑誌から、まずは基本のアクションと、そしてその応用の自分なりのアクションに発展させてきて、今の自分なりのアクションが生まれてきたかなと。
ちなみに、自分独自(かどうかは知りませんが、とりあえず自分で思いついたもの)のアクションの名前については、結構適当につけています。
ネーミングセンスがないのは、まあご愛嬌で^^;
ということで、今自分が主に使っている、スプーンのアクションをご紹介です。
カット:
これは、雑誌にもNeiちゃんのスプーンスタイルのDVDにも載っていましたが、単純に竿先を軽く上に跳ね上げるアクションですね。
一瞬ルアーが今までリトリーブしていた泳層のやや上に跳ね上がり、その後またもとの泳層へ戻るようなアクションらしいです。
なんというか、実に手っ取り早いアクションですね。
でも本当にこれを有効に使うためには、とにかく等速リトリーブが出来ていないと、まったく役に立たないかと思われます。
ちなみに、空あわせもこのアクションに分類されるかな!?(笑)
空あわせ後にも、よくバイトありますしね^^
ここからが、一応自分なりの応用編で、もしかしたら自分の知らないところで既出なのかもしれませんが、一応自分で考えたアクションです。
ダウンカット(仮):
カットが上に跳ね上げる動作に対して、下に向かってカットしています。
アクション的にはトゥイッチングに近いような、でもそれよりもぜんぜん軽い操作で行っています。
本当に竿先を、ピッと弾くような感じで。
ルアーの動きとしては、おそらく一瞬だけダッシュしてその後に一瞬だけ停止するような動作になっているかと思います。
おそらく下にカットする分、ルアーの浮き上がりは抑えられているはず。
カットと適宜組み合わせて使っています。
ホイップ(仮):
これは、ダウンカットを小さくやっているうちに生まれたアクションですね。
表層から中層でも上のほうで使っています。
どういうアクションかというと、竿先を細かく上下にカットするのですが、その際に竿先から水面まで延びているラインをムチのように上下に震わすような感じでアクションをつけています。
ラインで水面を軽くたたくようなイメージでしょうか。
ちょっと表現が難しいなぁ。
ルアーに対して直接アクションをかけるイメージではなく、ラインを動かすような軽いタッチで行います。
一応サイトで動きを確認すると、通常のスプーンのアクションに加えて、頭の部分が軽く上下しているようなアクションに見えました。
まあまだ研究中のアクションなので、どこまで有効で、本当にそんなアクションをし続けているのか、といった部分は未知数です。
スラッキング(仮):
これがまた偶然から生まれたもので、これについては自分の中ではかなり有効なアクションとして使っています。
やり方はいたって簡単で、普通にリトリーブしながらラインスラックを作るだけです。
要はリトリーブしつつ、時々竿先を水面まで落として、再び持ち上げるだけですね。
(ほんとうにラインスラックを作るだけ)
コツとしては、あまりすばやくやらないで、よっこいしょ、ってなくらいに落ち着いてやることでしょうか。
ルアーにかかるアクションとしてはおそらく、
一瞬停止>軽くダッシュ>一瞬停止>再度軽くダッシュ>通常速度
というような動きになっているかと思われます。
カットのようにバランスを崩すようなすばやい動きではないです。
大体このアクションで魚がバイトしてくるタイミングは、一番最後の通常のリトリーブ速度に戻る寸前あたりになります。
時々、最初の軽くダッシュ(竿先を水面につけようと落としている最中)でバイトがありますが、圧倒的に最後のラインスラックの完成したとき、つまり通常のリトリーブ位置に竿のポジションが戻った瞬間にバイトがあります。
ここまで読めば、どういった偶然で生まれたかは容易に予想できるかと思いますが、ラインであたりを取る際に、ラインスラックがあるとラインが見やすいというのはよくあることで、そのときも最初からラインスラックを作ってリトリーブしていました。
すると、途中でラインが見難くなってきたので、ラインスラックを作ろうと再度水面まで竿先を落として、持ち上げたその瞬間にバイトがあり、そのままゲットできました。
まあこれだけですと偶然だろうということで終わるのですが、このときはまったくこういったアクションについては無関心なときだったので、何も考えずにキャストを繰り返し、何も考えずにラインスラックを作り直し、その作り直し終わった瞬間にまたばかすかとバイトがあり、まさに爆釣状態に入ったため、後日あらためてそのときの状況を思い出してみると、偶然とは思えないほどの同じタイミングでのバイトということにようやく気がつきました。
その後も、慎重に他のエリアでもこのアクションを試してみたのですが、釣果のばらつきはあるものの、バイトがあるタイミングはほぼ同じで、これはもしかしてなかなか有効なアクションなのではないかと、とりあえず自分のメインのアクションとして使おうかなと思ったわけです。
どっちかというと、若干活性があるほうが、このアクションは有効っぽいかなと感じていますが、そこまではよくわかっていません。
はてさて一応自分が使っているスプーンのアクションを紹介してみましたが、こういったアクションでかかるかどうかは、そのときのお魚さんの気分によるので、アクションによる誘いが効かないときは、ぜんぜん効かないということはよくあるかと思います。

私は、そのときはあっさりとクランクに移行しちゃっています(笑)
えぇ、やっぱり楽しく簡単?に釣れればそれにこしたことはないですからね

てことで、素人に毛が生えた程度の考察でしたが、笑い飛ばしながらも参考にしてみてはいかが?
2006年06月26日
バイクへのロッドやネットの搭載方法です
バイクで釣りに行っている人や、また、こちらがバイクで来ていることを知ったばかりの人と話をすると、必ず聞かれる話題は、
どうやってロッド積んでいるの?
という話になります。
いやはや、同じバイク乗りだと、お互いの参考のための情報交換であり、またバイク乗りではない人にとっては、想像すると一番最初に思いつく苦労しそうな点なのでしょう。
いや、確かに悩みますよ、この問題は・・・
私が今まで話したところだと、やはり多いのがパックロッドを使用して鞄に詰め込む、というものでした。
あとはパイプなどをバイクにくくりつけて、その中に入れるという話も聞きました。
(特にスクーター系かな)
でもやはり、パックロッドが一番多いような感じです。
特に車などで来ている人と話をすると、「ロッドはやはりパックロッドですか?」と聞かれますが、私の場合、過去に記事に書いているように、2ピースロッドでがんばっています。
まあ確かにパックロッドのほうが楽なんですが、ロッドの説明書きなどを読むと、パックロッドについてはたいてい
1ピース(あるいは2ピース)ロッドのような自然なベントカーブ
とかいった、ロッドの具体的な性能説明じゃない部分しか紹介されていなくて、これじゃあまったく自分が欲しいものかどうかなんて判断できませんよ(仕舞い寸法やルアー重量、ライン強度などのデジタルな数値以外)、というとっても不親切なものとなっています。
だもんで、なぜかいつも通販野郎の自分としては、パックロッドはまったく検討の余地に入ってこないというわけなんですね。
いろいろと見ていったら、細かく説明があったパックロッドも見かけましたが、まあそれでも、普通に2ピースなどのロッドの説明のほうが、気合が入っているというか、そのロッドを勧めようという気合が説明書きから窺えます。
てことで、私の場合は、2ピースがメインとなっておりますが、そうすると、いかに安全に固定してロッドを積むかという問題を解決しなければなりません。
問題点としては、いかにロッドの飛び出してしまう部分について、安全性を高めるか、ということになるかと思います。
ということで、現在どのように積んでいるかの写真を紹介します。
 これは、バグスターのスポーツサドルバッグというサイドバッグなのですが、細長く設計されているため、ロッドのだいたい半分くらいを突っ込むことが出来ます。
これは、バグスターのスポーツサドルバッグというサイドバッグなのですが、細長く設計されているため、ロッドのだいたい半分くらいを突っ込むことが出来ます。
同時にネットも入れてお互いを固定することで、ロッドにかかる負荷の軽減も考えていますし、すっぽ抜け防止にもなっています。
(うまく想定通りになっているかどうかは別として^^;)
また、リアボックスをつけている関係上、サイドバッグからロッドやネットの柄が飛び出ていても、それよりも後ろにリアボックスがあるため、実質上、バイクからロッド部分が飛び出しているという印象はなくなります。
上から見た写真にもあるように、出来る限りリアボックスに接触するように固定してしまうため、見た目的にも特に危ないという印象もあまりないはずです。
サイドバッグの構造上、本来はこういう風にロッドのあまり部分やネットの柄などが飛び出ることを想定していないのですが、材質がナイロンであるため、またバッグの内側で、まずはマジックテープにより第1段階として内側の封をして閉める(これは写真には写っていません。バッグのふたを開けたその内側です)ことになり、その外側でもさらにマジックテープで最終的にふたを閉めることになるため、普通ならこれではふたが閉まらない状態ではあるのですが、ナイロンの柔らかさを利用して出来る限り押さえつけて、閉まる部分だけについてそのマジックテープで固定してしまうと、実はこれでロッドもすっぽ抜けることもなく、充分に固定できてしまいます。
高速道路ですっとばしても、何の問題も出ませんし、すり抜け自体も、特に気にすることはありません。
(写真では見にくいのですが、右側(後ろ側)について、マジックテープのB面がでていて、本来はそこまでふたがしまるということが、なんとかわかると思います。材質がナイロンだからこういった強引な技が出来ます)
とりあえず、現在はこういった積み方で、まったく問題はでていません。
でも、これ以上長いロッドは、ちょっと危ないかなと
さすがにバックに仕舞い寸法の半分も入らない状況だったり、リアボックスよりも長く後ろに出てしまったりすると、あまりにも危険でしょう。
ということで、他のバイク乗りのアングラーのみなさん、参考になりますでしょうか?
ちなみにこの、バグスターのスポーツサドルバッグは本来は両側に付きますが・・・
ヨシムラ管がずいぶんとアップで付いているため、右側がつけられません
夜なべして、左だけの1サイドバッグにするために、アタッチメントを自作しました。(ってほどのものは作ってないですけどね)
どうやってロッド積んでいるの?
という話になります。
いやはや、同じバイク乗りだと、お互いの参考のための情報交換であり、またバイク乗りではない人にとっては、想像すると一番最初に思いつく苦労しそうな点なのでしょう。
いや、確かに悩みますよ、この問題は・・・
私が今まで話したところだと、やはり多いのがパックロッドを使用して鞄に詰め込む、というものでした。
あとはパイプなどをバイクにくくりつけて、その中に入れるという話も聞きました。
(特にスクーター系かな)
でもやはり、パックロッドが一番多いような感じです。
特に車などで来ている人と話をすると、「ロッドはやはりパックロッドですか?」と聞かれますが、私の場合、過去に記事に書いているように、2ピースロッドでがんばっています。
まあ確かにパックロッドのほうが楽なんですが、ロッドの説明書きなどを読むと、パックロッドについてはたいてい
1ピース(あるいは2ピース)ロッドのような自然なベントカーブ
とかいった、ロッドの具体的な性能説明じゃない部分しか紹介されていなくて、これじゃあまったく自分が欲しいものかどうかなんて判断できませんよ(仕舞い寸法やルアー重量、ライン強度などのデジタルな数値以外)、というとっても不親切なものとなっています。
だもんで、なぜかいつも通販野郎の自分としては、パックロッドはまったく検討の余地に入ってこないというわけなんですね。
いろいろと見ていったら、細かく説明があったパックロッドも見かけましたが、まあそれでも、普通に2ピースなどのロッドの説明のほうが、気合が入っているというか、そのロッドを勧めようという気合が説明書きから窺えます。
てことで、私の場合は、2ピースがメインとなっておりますが、そうすると、いかに安全に固定してロッドを積むかという問題を解決しなければなりません。
問題点としては、いかにロッドの飛び出してしまう部分について、安全性を高めるか、ということになるかと思います。
ということで、現在どのように積んでいるかの写真を紹介します。
同時にネットも入れてお互いを固定することで、ロッドにかかる負荷の軽減も考えていますし、すっぽ抜け防止にもなっています。
(うまく想定通りになっているかどうかは別として^^;)
また、リアボックスをつけている関係上、サイドバッグからロッドやネットの柄が飛び出ていても、それよりも後ろにリアボックスがあるため、実質上、バイクからロッド部分が飛び出しているという印象はなくなります。
上から見た写真にもあるように、出来る限りリアボックスに接触するように固定してしまうため、見た目的にも特に危ないという印象もあまりないはずです。
サイドバッグの構造上、本来はこういう風にロッドのあまり部分やネットの柄などが飛び出ることを想定していないのですが、材質がナイロンであるため、またバッグの内側で、まずはマジックテープにより第1段階として内側の封をして閉める(これは写真には写っていません。バッグのふたを開けたその内側です)ことになり、その外側でもさらにマジックテープで最終的にふたを閉めることになるため、普通ならこれではふたが閉まらない状態ではあるのですが、ナイロンの柔らかさを利用して出来る限り押さえつけて、閉まる部分だけについてそのマジックテープで固定してしまうと、実はこれでロッドもすっぽ抜けることもなく、充分に固定できてしまいます。
高速道路ですっとばしても、何の問題も出ませんし、すり抜け自体も、特に気にすることはありません。
(写真では見にくいのですが、右側(後ろ側)について、マジックテープのB面がでていて、本来はそこまでふたがしまるということが、なんとかわかると思います。材質がナイロンだからこういった強引な技が出来ます)
とりあえず、現在はこういった積み方で、まったく問題はでていません。

でも、これ以上長いロッドは、ちょっと危ないかなと

さすがにバックに仕舞い寸法の半分も入らない状況だったり、リアボックスよりも長く後ろに出てしまったりすると、あまりにも危険でしょう。
ということで、他のバイク乗りのアングラーのみなさん、参考になりますでしょうか?
ちなみにこの、バグスターのスポーツサドルバッグは本来は両側に付きますが・・・
ヨシムラ管がずいぶんとアップで付いているため、右側がつけられません

夜なべして、左だけの1サイドバッグにするために、アタッチメントを自作しました。(ってほどのものは作ってないですけどね)
2006年06月21日
スティックルアーってどうなんだろう!?
どうなんだろうって言うのは、まあとにかく、
本当に簡単に釣れるの!?
ってことなんですが、どうなんでしょうねぇ。
いや、先日の発光路の森でもそうでしたが、スティックルアーやスティックスプーンを使っている人はいましたが、その人たちが爆釣していたかというと、ぜんぜんそんなことはなかったんですよ。
普通にスプーンを使っていた私のほうが、地道に釣れていましたし。
しかし一度は、すそのフィッシングパークで、
おぉ、すげ~あの人だけ一人釣れている~、何使っているんだろう~
ていうことがあり、それはX-スティックだったということもありました。
やっぱり要は、
使いこなせるかどうか
ってことだけなんだろうなぁ。
雑誌等々で、「釣れすぎる」だのなんだの書いてあって、初心者でも簡単に釣れるような印象を与え続けていますが、結局は使いこなせなきゃ、釣れる釣れないは、どのルアーも一緒かなと、最近ちょっと思っています。
たぶんきっと、初心者でも正しく教えれば、きちんと使いこなせるのがスティックルアーなんでしょう。
逆に正しく教えられない、正しく使いきれない場合は、もしかして普通のルアー以下!?
てことで、誰かスティックルアーの使い方、教えて^^;
(結局は、使い方を知りたいだけ(笑))
自慢じゃないが、X-スティックでは、バイト数1で釣り上げ数0でございますぞ(笑)
(ACスティックスプーンでは自慢じゃないが、バイト数も0だ!!)
しかし、なんでこれで禁止ルアーになるのかな?
釣れすぎというイメージは、今のところぜんぜんないですけどね。
渋いときにも釣れるって言うけど、実際にそんな状況でスティックルアーを使って釣れている人は1度(前記のすその)しか見たことないので、大半はスティックルアー使っている人を見ていても、それほど釣れている印象はないですしね。
でも、1度だけ見たその渋い中スティックルアーでバンバン釣っていた状況ですが、渋いといってもスプーンでもがんばってぽつぽつ上がる状況ではあったので、激シブってわけではなかったです。
(でも、釣果の差は歴然としていましたけどね。そのときは、スティックのすごさに驚きを隠せませんでしたが。だもんで、その後すぐにX-スティックを買っちゃいました(笑))
お、そういえば、王様規定のルールでも、たしかスティックは禁止じゃなかったはずだ!!
(2cm未満のルアーは禁止だけどね)
よし今度、あらためてスティックルアーの練習してみよっと。
これで爆釣したら、この記事の立場ないな(笑)
本当に簡単に釣れるの!?
ってことなんですが、どうなんでしょうねぇ。
いや、先日の発光路の森でもそうでしたが、スティックルアーやスティックスプーンを使っている人はいましたが、その人たちが爆釣していたかというと、ぜんぜんそんなことはなかったんですよ。
普通にスプーンを使っていた私のほうが、地道に釣れていましたし。
しかし一度は、すそのフィッシングパークで、
おぉ、すげ~あの人だけ一人釣れている~、何使っているんだろう~
ていうことがあり、それはX-スティックだったということもありました。
やっぱり要は、
使いこなせるかどうか
ってことだけなんだろうなぁ。
雑誌等々で、「釣れすぎる」だのなんだの書いてあって、初心者でも簡単に釣れるような印象を与え続けていますが、結局は使いこなせなきゃ、釣れる釣れないは、どのルアーも一緒かなと、最近ちょっと思っています。
たぶんきっと、初心者でも正しく教えれば、きちんと使いこなせるのがスティックルアーなんでしょう。
逆に正しく教えられない、正しく使いきれない場合は、もしかして普通のルアー以下!?
てことで、誰かスティックルアーの使い方、教えて^^;
(結局は、使い方を知りたいだけ(笑))
自慢じゃないが、X-スティックでは、バイト数1で釣り上げ数0でございますぞ(笑)
(ACスティックスプーンでは自慢じゃないが、バイト数も0だ!!)
しかし、なんでこれで禁止ルアーになるのかな?
釣れすぎというイメージは、今のところぜんぜんないですけどね。
渋いときにも釣れるって言うけど、実際にそんな状況でスティックルアーを使って釣れている人は1度(前記のすその)しか見たことないので、大半はスティックルアー使っている人を見ていても、それほど釣れている印象はないですしね。
でも、1度だけ見たその渋い中スティックルアーでバンバン釣っていた状況ですが、渋いといってもスプーンでもがんばってぽつぽつ上がる状況ではあったので、激シブってわけではなかったです。
(でも、釣果の差は歴然としていましたけどね。そのときは、スティックのすごさに驚きを隠せませんでしたが。だもんで、その後すぐにX-スティックを買っちゃいました(笑))
お、そういえば、王様規定のルールでも、たしかスティックは禁止じゃなかったはずだ!!
(2cm未満のルアーは禁止だけどね)
よし今度、あらためてスティックルアーの練習してみよっと。
これで爆釣したら、この記事の立場ないな(笑)
2006年06月15日
いろいろなロッドを使ってみて・・・
わずか9ヶ月の間に、ふと気がつくとロッドをたくさん買ってしまっていたのね~と、自分の計画性のなさにあきれつつも、自分なりのインプレッションでも書いておけば、今後、そのインプレがどのように変わっていくかで、まあ自分の釣り方などを見直すことが出来るかもしれないなぁ、ってことで、書いてみます。
でも、あくまで私が勝手に思っていることを書くのであって、人それぞれでインプレは変わってくると思うし、私がこういったから、思い切って買ったのに違うじゃないか~、といわれても、責任は取れませんのであしからず
 まずは、現在メインとなっている、ごく最近購入したバックウォータスペシャル<ボロン>(BWS-55T)から。
まずは、現在メインとなっている、ごく最近購入したバックウォータスペシャル<ボロン>(BWS-55T)から。
正直、何に特化しているとかいうのはいまいちわからないところですが、スプーンを使ったときにシャープにキャストできて、切れよくあわせられるという印象です。
なので、クランクについては、本当に使いにくい印象があります。
ミノーについては、なんとなくきびきび動かせるかな?って感じですね。
魚がかかると、よく曲がり、魚のすばやい動きに追従していきますが、でも主導権はわたさずに、しっかりと魚の動きを制御してくれます。
スプーニングメインということで、リールはステラのダブルハンドルを使用しています。
一番手前のガイドの径が小さいので、1000番以下のリールで軽いものがよいでしょう。
 次に、ちょっと前まではメインで、一番使っているストリームスピン<ボロン>(SS-52EXL)です。
次に、ちょっと前まではメインで、一番使っているストリームスピン<ボロン>(SS-52EXL)です。
これは、本当に何でも出来るという印象です。スプーンもクランクも。
ミノーについてはちょびっともたって印象を持ってしまいますが、まあミノーはぜんぜん使いこなせていないので、あまり参考にしないでください。
また、クランクについては、あまりにも完璧ではないかと思えるくらいのバランスです。(私の印象ですよ、あくまで)
柔軟なティップがクランクにバイトしてきた魚に十分くわえ込むだけのゆとりを与えていて、しかし、バット部のボロンが効いているのか、柔らかいだけではなく強さも持っているため、十分に食いついてきた魚に、ガツン(まあ、正確にはどっこいしょ~、かな^^;)とフッキングすることができて、とにかくクランクについては、私が持っているロッドのなかで、頭3つくらい抜け出ているほど、すごく使い勝手がよい印象です。(これ以外のロッドでクランクを引くとストレスが^^;)
こいつでクランクで引いてかからなければ、まあしょうがないか~って思えるくらいですね。
こいつも全体的にみると柔らかいので、魚がかかるとかなり曲がっていきますが、でも魚に主導権をとられるということもなく、十分に制御できます。
ですがバックウォータスペシャル<ボロン>(BWS-55T)に比べると、全体的に動きがトロい印象を受けます。
べなって感じは以前はしなかったのですが、比べるとそんな感じにも思ってしまいます。
魚への制御力もバックウォータスペシャル<ボロン>(BWS-55T)のほうがある感じです(操りやすい)。
ですが、まさにオールマイティなロッドです。
クランキングメインという理由ではないのですが、見た目を重視でリールはステラのダブルハンドルをシングルハンドルに変えたものを使用しています。
クランクであれば、引き抵抗が強いので、デッドスローにもっていったときでも、シングルハンドルとダブルハンドルの差は、あまりありません。
そうそう、王様こと村田基氏は、ダブルハンドルは速巻きすることがあまりない管理釣り場では、あまり効果がないと言っていますが、物理的に言って、ありえません(笑)
速巻きすることが多いのであれば、ダブルハンドルは必要なく、遅巻きする必要があればあるほどダブルハンドルの効果は物理的に言って絶大です。
まあ、物理的といっても、本当にちょっと考えればわかることで、ハンドルにかかる抵抗力や、重力、巻くときにかける力などをざっくりと書けば、すぐにわかる話です。
現にメーカーだって、そう思っているから管理釣り場用のリールにダブルハンドルをつけて出しているんですよ。
でもきっと、王様くらいになると、別の要素が働いて、速巻きのほうに絶大な効果が出るのかもしれません。
これは馬鹿にしていっているのではなく、釣りということに対して真剣な人が、そんな馬鹿な間違いをするとは思えないからです。
でも、物理的にみれば、間違いですので、そうですね、本当に釣り道具を使いこなしきれるという人以外は、ダブルハンドルは、遅巻き用だと思って間違いないと思います。
(でも意外と間違いだったりして^^;)
閑話休題
ここからは、あまり使用していないロッドなので、ざっくりと。
コータックSWELLは、まさにべなべななグラスロッドです。
ただ、チューブラーなので軽く扱いやすいロッドではあります。
あまり引き抵抗の強いクランクは、辛いですが、MRからSR程度のクランクであれば、食い込みもよく使い勝手はよいです。
どちらかというと典型的なのせ竿です。
初心者に使ってもらって、勝手に魚をかけてくれるという便利のよいロッドなので、そういった目的で現在所有しています。
大き目の魚がかかると、ぐいぐいもっていかれて、制御不能になることも(笑)
それはそれで楽しいともいいます(笑)
スウィートウォータ(SWP-665L)ですが、基本的に硬いロッドなのですが、6.6ftもあるおかげで、柔らかく感じられます。
ですが、これに小さい魚がかかると、かかっているんだかいないんだかわからない状態で、手元まで引っ張って来れます(笑)
こいつでかけた50cm台のドナルドソンを、ストリームスピン<ボロン>(SS-52EXL)でかけた35~40cm前後とあまり変わらないくらい印象を与えるほどのパワーをもっています。
ストリームトゥイッチャー<ボロン>(TS-52UL)ですが、これも硬いロッドです。
ミノーイングには、きっと最高なんでしょうが、自分がミノーをうまく使えない時点で、このロッドの性能をまったく引き出していません^^;
まあ、これから修行していくうちに、新たな感動が生まれると信じて、今は冬眠?中です^^;
ちなみに、これでマルミのドナルドソンをあげていますが、ストリームスピン<ボロン>(SS-52EXL)に比べると、楽勝で引っ張って来れます(笑)
ざっとまとめると・・・こんな感じでしょうか。
(あくまでトラウト管理釣り場でよく使うルアーで考えてくださいね)
評価としては、◎>○>△>▲>×って感じで自分の印象を書いています。
上記に書いた特性以外でも、遠投性や、キャスティングのしやすさ、コントロール性やいろいろとありますので、あくまでこれは参考レベル、しかも初心者からちょっと抜け出したレベルの人間が評価したものとして、見てください。
ところで、気がつきましたでしょうか?
そうですロッドの長さは基本的に5.6ft以下のものしか使っていないんです。
スウィートウォータが6.6ftありますが、これは5ピースに分かれるパックロッドです。
そうです、バイクに乗せていくために、仕舞い寸法が短くないといけないため、今現在は、5.6ftより長くて2ピース以下のロッドについては、購入対象外になっています。
なので、メインは5.6ft以下の2ピースロッドとなっています。
でも、ある程度の長さは確保したい・・・ってことで、短いシングルグリップのものがメインになっています。
今もっているufmのロッドのグリップ部分は短いですよ~。
グリップ部分が短い分、実際に有効なロッドの部分は長くなりますからね。
衝動買い的に買ってはいますが、実はいろいろと考えて買っているんです。
ほんと、バイクにロッドを積むのは大変なんですよ
でも、あくまで私が勝手に思っていることを書くのであって、人それぞれでインプレは変わってくると思うし、私がこういったから、思い切って買ったのに違うじゃないか~、といわれても、責任は取れませんのであしからず

正直、何に特化しているとかいうのはいまいちわからないところですが、スプーンを使ったときにシャープにキャストできて、切れよくあわせられるという印象です。
なので、クランクについては、本当に使いにくい印象があります。
ミノーについては、なんとなくきびきび動かせるかな?って感じですね。
魚がかかると、よく曲がり、魚のすばやい動きに追従していきますが、でも主導権はわたさずに、しっかりと魚の動きを制御してくれます。
スプーニングメインということで、リールはステラのダブルハンドルを使用しています。
一番手前のガイドの径が小さいので、1000番以下のリールで軽いものがよいでしょう。
これは、本当に何でも出来るという印象です。スプーンもクランクも。
ミノーについてはちょびっともたって印象を持ってしまいますが、まあミノーはぜんぜん使いこなせていないので、あまり参考にしないでください。
また、クランクについては、あまりにも完璧ではないかと思えるくらいのバランスです。(私の印象ですよ、あくまで)
柔軟なティップがクランクにバイトしてきた魚に十分くわえ込むだけのゆとりを与えていて、しかし、バット部のボロンが効いているのか、柔らかいだけではなく強さも持っているため、十分に食いついてきた魚に、ガツン(まあ、正確にはどっこいしょ~、かな^^;)とフッキングすることができて、とにかくクランクについては、私が持っているロッドのなかで、頭3つくらい抜け出ているほど、すごく使い勝手がよい印象です。(これ以外のロッドでクランクを引くとストレスが^^;)
こいつでクランクで引いてかからなければ、まあしょうがないか~って思えるくらいですね。
こいつも全体的にみると柔らかいので、魚がかかるとかなり曲がっていきますが、でも魚に主導権をとられるということもなく、十分に制御できます。
ですがバックウォータスペシャル<ボロン>(BWS-55T)に比べると、全体的に動きがトロい印象を受けます。
べなって感じは以前はしなかったのですが、比べるとそんな感じにも思ってしまいます。
魚への制御力もバックウォータスペシャル<ボロン>(BWS-55T)のほうがある感じです(操りやすい)。
ですが、まさにオールマイティなロッドです。
クランキングメインという理由ではないのですが、見た目を重視でリールはステラのダブルハンドルをシングルハンドルに変えたものを使用しています。
クランクであれば、引き抵抗が強いので、デッドスローにもっていったときでも、シングルハンドルとダブルハンドルの差は、あまりありません。
そうそう、王様こと村田基氏は、ダブルハンドルは速巻きすることがあまりない管理釣り場では、あまり効果がないと言っていますが、物理的に言って、ありえません(笑)
速巻きすることが多いのであれば、ダブルハンドルは必要なく、遅巻きする必要があればあるほどダブルハンドルの効果は物理的に言って絶大です。
まあ、物理的といっても、本当にちょっと考えればわかることで、ハンドルにかかる抵抗力や、重力、巻くときにかける力などをざっくりと書けば、すぐにわかる話です。
現にメーカーだって、そう思っているから管理釣り場用のリールにダブルハンドルをつけて出しているんですよ。
でもきっと、王様くらいになると、別の要素が働いて、速巻きのほうに絶大な効果が出るのかもしれません。
これは馬鹿にしていっているのではなく、釣りということに対して真剣な人が、そんな馬鹿な間違いをするとは思えないからです。
でも、物理的にみれば、間違いですので、そうですね、本当に釣り道具を使いこなしきれるという人以外は、ダブルハンドルは、遅巻き用だと思って間違いないと思います。
(でも意外と間違いだったりして^^;)
閑話休題
ここからは、あまり使用していないロッドなので、ざっくりと。
コータックSWELLは、まさにべなべななグラスロッドです。
ただ、チューブラーなので軽く扱いやすいロッドではあります。
あまり引き抵抗の強いクランクは、辛いですが、MRからSR程度のクランクであれば、食い込みもよく使い勝手はよいです。
どちらかというと典型的なのせ竿です。
初心者に使ってもらって、勝手に魚をかけてくれるという便利のよいロッドなので、そういった目的で現在所有しています。
大き目の魚がかかると、ぐいぐいもっていかれて、制御不能になることも(笑)
それはそれで楽しいともいいます(笑)
スウィートウォータ(SWP-665L)ですが、基本的に硬いロッドなのですが、6.6ftもあるおかげで、柔らかく感じられます。
ですが、これに小さい魚がかかると、かかっているんだかいないんだかわからない状態で、手元まで引っ張って来れます(笑)
こいつでかけた50cm台のドナルドソンを、ストリームスピン<ボロン>(SS-52EXL)でかけた35~40cm前後とあまり変わらないくらい印象を与えるほどのパワーをもっています。
ストリームトゥイッチャー<ボロン>(TS-52UL)ですが、これも硬いロッドです。
ミノーイングには、きっと最高なんでしょうが、自分がミノーをうまく使えない時点で、このロッドの性能をまったく引き出していません^^;
まあ、これから修行していくうちに、新たな感動が生まれると信じて、今は冬眠?中です^^;
ちなみに、これでマルミのドナルドソンをあげていますが、ストリームスピン<ボロン>(SS-52EXL)に比べると、楽勝で引っ張って来れます(笑)
ざっとまとめると・・・こんな感じでしょうか。
| 特性 | BWS-55T | SS-52EXL | SWELL | SWP-665L | TS-52UL |
|---|---|---|---|---|---|
| スプーン | ◎ | ○ | ○ | △ | △ |
| クランク | × | ◎ | △ | △ | △ |
| ミノー | ○ | ▲ | × | ○ | ◎ |
| テーパー | スロー気味のレギュラーかな | レギュラー | レギュラー | ファストかな | レギュラー |
| 30cm未満の魚とのやり取り | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ |
| 30cm~40cm | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 50cm~ | ○ | △ | × | ◎ | ◎ |
評価としては、◎>○>△>▲>×って感じで自分の印象を書いています。
上記に書いた特性以外でも、遠投性や、キャスティングのしやすさ、コントロール性やいろいろとありますので、あくまでこれは参考レベル、しかも初心者からちょっと抜け出したレベルの人間が評価したものとして、見てください。
ところで、気がつきましたでしょうか?
そうですロッドの長さは基本的に5.6ft以下のものしか使っていないんです。
スウィートウォータが6.6ftありますが、これは5ピースに分かれるパックロッドです。
そうです、バイクに乗せていくために、仕舞い寸法が短くないといけないため、今現在は、5.6ftより長くて2ピース以下のロッドについては、購入対象外になっています。
なので、メインは5.6ft以下の2ピースロッドとなっています。
でも、ある程度の長さは確保したい・・・ってことで、短いシングルグリップのものがメインになっています。
今もっているufmのロッドのグリップ部分は短いですよ~。
グリップ部分が短い分、実際に有効なロッドの部分は長くなりますからね。
衝動買い的に買ってはいますが、実はいろいろと考えて買っているんです。
ほんと、バイクにロッドを積むのは大変なんですよ

2006年06月08日
ロデオフィッシュばっかりだ(笑)
え、何がっていうと、このBLOGへアクセスしに来た時のここ1ヶ月の検索キーですよ。
あまりにもぶっちぎりの状態でした。
1位 ロデオフィッシュ 300アクセスオーバー
2位 あずみ野 17アクセス
(この検索キーで検索エンジンとかから本BLOGにアクセスしてきた数ですよ、この数は)
桁が違いますって(笑)
実は3位以下にも、ロデオフィッシュで検索しに来たカウントがあるので、まさにロデオフィッシュだけでこのBLOGは検索されているのか!?って状態です。
しかし、ここまで気になるのであれば、みんなロデオフィッシュに行ってみればいいのにねぇ。
先日は結構今まで行った中では人がいたほうですが、でもすごくゆとりを持って釣りが出来ますよ。
でも、今まで週末に行って、一番すいていたのは、レイクフォレストだったり、尾瀬FLだったりしますが。
なお、ロデオフィッシュを除くと、他の検索キーでアクセスしに来るのは、あずみ野FCであったり槻の池であったりと、こういったところを見ると、世間の興味がどうなっているかわかったりして、面白いですね。
おそらく、情報量が少ないエリアで、かつ雑誌等で話題になったものに対してやはりアクセスが多くなるのかな、と想像できます。
ちなみに、このBLOGの当初での検索キーのトップは槻の池でした。
まあ、釣り研究じゃないけど、BLOGの検索キー研究ってことで(笑)
あまりにもぶっちぎりの状態でした。
1位 ロデオフィッシュ 300アクセスオーバー
2位 あずみ野 17アクセス
(この検索キーで検索エンジンとかから本BLOGにアクセスしてきた数ですよ、この数は)
桁が違いますって(笑)
実は3位以下にも、ロデオフィッシュで検索しに来たカウントがあるので、まさにロデオフィッシュだけでこのBLOGは検索されているのか!?って状態です。
しかし、ここまで気になるのであれば、みんなロデオフィッシュに行ってみればいいのにねぇ。
先日は結構今まで行った中では人がいたほうですが、でもすごくゆとりを持って釣りが出来ますよ。
でも、今まで週末に行って、一番すいていたのは、レイクフォレストだったり、尾瀬FLだったりしますが。
なお、ロデオフィッシュを除くと、他の検索キーでアクセスしに来るのは、あずみ野FCであったり槻の池であったりと、こういったところを見ると、世間の興味がどうなっているかわかったりして、面白いですね。
おそらく、情報量が少ないエリアで、かつ雑誌等で話題になったものに対してやはりアクセスが多くなるのかな、と想像できます。
ちなみに、このBLOGの当初での検索キーのトップは槻の池でした。
まあ、釣り研究じゃないけど、BLOGの検索キー研究ってことで(笑)
2006年06月06日
これまでの自分の釣果を分析です
前回は、ざっと行ったエリア数だけを数えましたが、今回は、もうちょっといろいろな数字を集めてみました。
表1 エリア別釣行回数(2005年9月~2006年6月4日)
こうやって見ると、やはりFO!王禅寺は近いだけあって、結構行っていますね。
ただ、一番回数をこなしている割には、釣果が伸びていないのは、あまり数が出ないエリアということになるのでしょうか?
とはいえ、実際のところは、キャスティングの練習に行ったりとか、ルアーに縛りをかけて釣りをしたりとかと、いうなれば普通に釣りをしていないので、数が伸びていないのかもしれません。
一番数が出ているのが、先日たくさん釣れたロデオフィッシュですが、実は最後の数を抜かすと、3匹、4匹、7匹とあまり釣れていません。
最後の釣行では、朝一から最終までやっていたため、数が伸ばせたのでしょう。
やはり朝一に入ると、釣果がぜんぜん違いますね。
FO!鹿留も数が出ていますが、これも偶然にも鹿留湖で爆釣モードに入ったときがあったためで、残りの釣果は1桁だったりします。
同じエリアにあまり行っていないせいで、平均を出したところで参考にもなりませんし、やはりここから何らかの傾向を分析するにはデータが不足しているようです。
しかし、312匹も釣っていたんですね。8ヶ月で。1ヶ月39匹ですか。う~ん、多いのか少ないのかよくわかりませんね。
自分的には多く感じますが、どうなんでしょうかね。
釣行回数で合計を割った、1釣行あたりの平均引数は7.4匹です。
やっぱり少ないのかな?
でも、まだ始めたばっかりのころの5匹もつれないときというのもありますから、今ならもうちょっと平均が高いかもしれません。
ということで、次は月別に集計してみましょう。
表2 月ごとの釣行回数と釣果(2005年10月~2006年5月)
9月と6月は、ともに回数が少ないので除いています。
徐々に釣果が伸びてきているようですね。
1月~3月の間で釣果が伸びてきているのは、ちょうどそのころにラインであたりが取れるようになったからでしょう。(平均釣果を超えていますね)
4月は、天候がいまいちだったのかな?(暑かったかな)
4月の最初に行った尾瀬以外は、かなり苦戦しているようです。
5月は、レイクフォレストやあずみ野など、涼しい地域での釣行(でも暑かったけど^^;)があったせいか、若干盛り返しています。
こうしてみると、やはり3月あたりが釣りやすいのかもしれません。
これから夏場にかけて、どういった集計が取れるのか、ちょっと楽しみです。
何ヶ月かに1度、こういった集計を取ってみると、釣果の変動がわかって、参考になりそうですね。
そうそう追記です。
おそらく管理釣り場に通いなれている人からすれば、全然、数釣れていないじゃないか~、とか言われそうですが、ルアーフィッシング自体を始めたのが去年の9月(このBLOGの最初の日付)からで、オール自己流、雑誌やインターネットなどを参考にすることはありますが、実際には自分の観察と小さいころにやっていた釣りの経験だけでやっているわけで、自分自身でこそっと毎回課題を決めて練習をしていたりするし、そう考えるとがんばったほうじゃないのかな?
(と自己弁護してみたりする(笑))
そうそう、後はひらめきと物理的な考えを少々と、とにかく楽しんでやること、で徐々に上達していっている(と思う)わけですよ。
表1 エリア別釣行回数(2005年9月~2006年6月4日)
| エリア名 | 釣行回数 | 全釣果 |
|---|---|---|
| FO!王禅寺 | 7 | 26 |
| FO!鹿留(パインレイク) | 4 | 34 |
| FW小山エリア | 4 | 18 |
| ロデオフィッシュ | 4 | 42 |
| マルミFA | 3 | 9 |
| あずみ野FC | 2 | 19 |
| 加賀FA | 2 | 11 |
| すそのFP | 2 | 20 |
| 柿田川FS | 2 | 16 |
| 槻の池 | 2 | 1 |
| 尾瀬FL | 1 | 19 |
| 鹿島槍ガーデン | 1 | 7 |
| レイクフォレスト | 1 | 19 |
| ジョイバレー | 1 | 17 |
| 朝霞ガーデン | 1 | 20 |
| BIGROCK | 1 | 6 |
| 東山湖 | 1 | 20 |
| アングラーズエリアHOOK | 1 | 5 |
| レイクウッドリゾート | 1 | 2 |
| 竜華池 | 1 | 1 |
| 合計 | 42 | 312 |
こうやって見ると、やはりFO!王禅寺は近いだけあって、結構行っていますね。
ただ、一番回数をこなしている割には、釣果が伸びていないのは、あまり数が出ないエリアということになるのでしょうか?
とはいえ、実際のところは、キャスティングの練習に行ったりとか、ルアーに縛りをかけて釣りをしたりとかと、いうなれば普通に釣りをしていないので、数が伸びていないのかもしれません。
一番数が出ているのが、先日たくさん釣れたロデオフィッシュですが、実は最後の数を抜かすと、3匹、4匹、7匹とあまり釣れていません。
最後の釣行では、朝一から最終までやっていたため、数が伸ばせたのでしょう。
やはり朝一に入ると、釣果がぜんぜん違いますね。
FO!鹿留も数が出ていますが、これも偶然にも鹿留湖で爆釣モードに入ったときがあったためで、残りの釣果は1桁だったりします。
同じエリアにあまり行っていないせいで、平均を出したところで参考にもなりませんし、やはりここから何らかの傾向を分析するにはデータが不足しているようです。
しかし、312匹も釣っていたんですね。8ヶ月で。1ヶ月39匹ですか。う~ん、多いのか少ないのかよくわかりませんね。
自分的には多く感じますが、どうなんでしょうかね。
釣行回数で合計を割った、1釣行あたりの平均引数は7.4匹です。
やっぱり少ないのかな?
でも、まだ始めたばっかりのころの5匹もつれないときというのもありますから、今ならもうちょっと平均が高いかもしれません。
ということで、次は月別に集計してみましょう。
表2 月ごとの釣行回数と釣果(2005年10月~2006年5月)
| 年月 | 釣行回数 | 全釣果 | 平均釣果 |
|---|---|---|---|
| 2005年10月 | 7 | 35 | 5 |
| 2005年11月 | 5 | 24 | 4.8 |
| 2005年12月 | 6 | 25 | 4.2 |
| 2006年1月 | 2 | 11 | 5.5 |
| 2006年2月 | 3 | 25 | 8.3 |
| 2006年3月 | 5 | 63 | 12.6 |
| 2006年4月 | 5 | 31 | 6.2 |
| 2006年5月 | 7 | 69 | 9.9 |
| 合計 | 40 | 283 | 7 |
徐々に釣果が伸びてきているようですね。
1月~3月の間で釣果が伸びてきているのは、ちょうどそのころにラインであたりが取れるようになったからでしょう。(平均釣果を超えていますね)
4月は、天候がいまいちだったのかな?(暑かったかな)
4月の最初に行った尾瀬以外は、かなり苦戦しているようです。
5月は、レイクフォレストやあずみ野など、涼しい地域での釣行(でも暑かったけど^^;)があったせいか、若干盛り返しています。
こうしてみると、やはり3月あたりが釣りやすいのかもしれません。
これから夏場にかけて、どういった集計が取れるのか、ちょっと楽しみです。
何ヶ月かに1度、こういった集計を取ってみると、釣果の変動がわかって、参考になりそうですね。
そうそう追記です。
おそらく管理釣り場に通いなれている人からすれば、全然、数釣れていないじゃないか~、とか言われそうですが、ルアーフィッシング自体を始めたのが去年の9月(このBLOGの最初の日付)からで、オール自己流、雑誌やインターネットなどを参考にすることはありますが、実際には自分の観察と小さいころにやっていた釣りの経験だけでやっているわけで、自分自身でこそっと毎回課題を決めて練習をしていたりするし、そう考えるとがんばったほうじゃないのかな?
(と自己弁護してみたりする(笑))
そうそう、後はひらめきと物理的な考えを少々と、とにかく楽しんでやること、で徐々に上達していっている(と思う)わけですよ。